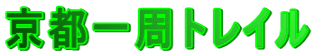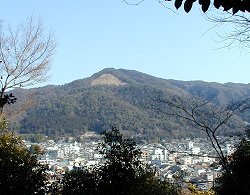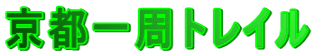
東山コース
(第二部:蹴上から銀閣寺まで)
2002・2・16
| 晴れ、暖かい一日でしたのでちょっとコース外を歩きすぎて疲れました。JR山科駅で京阪の京津線に乗り換える。二駅で京の出発点の蹴上だ。9:30 蹴上駅を出発。今日もインターネットからプリントアウトした案内地図をもっている。案内地図を頼りに1号線の歩道橋を渡りインクラインの軌道跡を日向大神宮へ向かう。 |
|

今日、歩いたコースです。
|

| インクライン跡に保存してある舟を運ぶ貨車と舟。名前は知っていたがはじめて歩く道である。 |
|
インクライン
逢坂山や日ノ岡の峠道は貨物輸送にとって難所、琵琶湖から水を引き、その水路を利用して舟運を興す夢が疏水の開削(明治18年起工1885)により可能になった。「疏水」はその他、かんがい、水力発電等多くの目的をもっていた。インクライン(傾斜鉄道)は疏水の水で発電された電力で、この坂を舟ごと上下させる。これで琵琶湖と淀川が疏水で結ばれ、北陸や近江、あるいは大阪から人や物資の往来が可能になった。昭和の初期まで盛んに利用され今日の京都の発展に寄与した。運転開始:明治24年、延長:582m勾配:1/15(の案内板より) |
|

日向大神宮
|

トレールコースの入り口
|
| インクライン跡の終わりに発電所がある。疏水に架かる大神宮橋を渡り、鳥居のあるコンクリート道の参道を登っていくと右の写真のところに出る。左手に石段があり登ると「日向大神宮」がありました。手前が外宮、奥の社が内宮。天照大御神が祭ってあり、天岩戸もあるんですよ。日向大神宮に参拝していよいよ山道に入る。(10:27) |
|
 |
 |
| 日向大神宮からはすぐ階段状の登りになる。振り返って神社のほうを撮る。階段状の道は約6分ほどで終わり、急な山道になる。やたらとトレールの道標が目につく。34,35,36,37に続いてNO.39の七福思案処の分岐に着く(10:44)。 |
|
| 七福思案処の分岐、ここは南禅寺、山科毘沙門堂などからの道が合流している。ここから「大文字山」に向けて進む。NO.41の道標を過ぎたころちょっと展望が開けた所があり京都の町、真下に平安神宮の赤い鳥居が見えた。 |
|
| 雑木林の尾根歩きが続きやがてNO.45の大文字山頂上の手前の分岐点に着いた。トレールはここで左折鹿ガ谷へ下ることになるがせっかくだから大文字山の頂上まで行くことにした。 |
|

|
 |
| 頂上はちょっとした広場となっていて京都市街が一望できる。右の写真の男性三人が立っている所は国土地理院の「NO.29基本菱形基点測点」です。その手前にあるのが大文字山の三等三角点です。 |
|
| 頂上でのんびりしたせいか下山で道を間違えてもと来た蹴上へ向かってしまう。道標NO.45で鹿ガ谷とあったのに、逆から見ると景色が変わって見える。道標44−2まで行って間違いに気づく(^_^;)。 |
|

| 山道が終わり舗装された道に出ると、浪切不動尊がある。 |
|

| 鹿ヶ谷への下山道。ちょっと急な石段などがあり今までの歩きやすい道とは違う。この石段の右手には楼門の滝がある。 |
|

| 舗装道路沿いには料亭や民家が並ぶ、京都の町の向こうには愛宕山が霞んで見えていた。 |
|

| このお寺のそばにあるNO.48の道標で右折。法然院経由で銀閣寺へ向かう。 |
|

法然院のかやぶきの山門は
いい感じだなあ
|

法然院の庭を散策してから
銀閣寺へ向う。
|
| 13:24 やっと銀閣寺につく。さすがメジャーな観光スポットだ、観光客でにぎわっている。時間があるので拝観料500円を払い入場しました。 |
|

銀閣寺総門
|

銀 閣
(観音殿・国宝)
| 鹿苑寺の舎利殿(金閣)、西芳寺の瑠璃殿を踏襲し、本来観音堂とよばれた。二層からなり一層の心空殿は書院風。二層の潮音閣は板壁に花頭窓(かとうまど)をしつらえて、桟唐戸を設けた唐様仏殿の様式。閣上にある金銅の鳳凰は東面し、観音菩薩を祀る銀閣を絶えず守り続けている。・・・・・パンプレッとより |
|

銀沙灘
知識持ち合わせていないから
造形の意味はわかりません(^_^;)。
|
銀閣寺の発祥
銀閣寺は臨済宗相国寺派に属する禅寺で建立は文明14年(1482)室町幕府八代将軍足利義政公による。銀閣寺は臨済宗相国寺は派に属する禅寺で、義政公は、祖父にあたる三代将軍足利義満公の北山殿金閣(鹿苑寺)にならい、隠栖生活をすごすため山荘東山殿を造営。この東山殿が銀閣寺の発祥である。銀閣寺は俗称でであり、正しくは東山慈照寺。義政公の法号慈照院にちなみ後にこう命名された。
|
|

銀閣寺の庭を周遊。山手の高台から吉田山が展望できる。
銀閣寺の竹藪の向こうにこんもりとした森(吉田山)が見える。節分のとき行けなかったので帰り道立ち寄ってみよう。 |
|

| 銀閣寺を後に京都大学前の吉田山に向かう。振り返れば大文字山が・・・ |
|
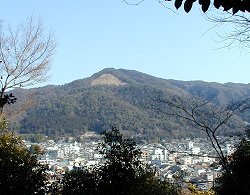
吉田山より大文字山が見える。
|

| 吉田山頂上から吉田神社へ向かうと三等三角点があった。105.12m設置明治36年(1903) |
|

|
| まだ時間が早いのでJR京都駅まで歩くことにする。いつもザックの中に持っている西国三十三箇所観音の納経帖のこと思い出して「六波羅蜜寺」に立ち寄る。ここには「平清盛公の塚」もありました。 |
|

|
 |
六波羅蜜寺
|
| 良い天気につられて良く歩いた一日でした。トレールのコースより帰り道が長かったです。疲れました(^_^)。 |
|
|