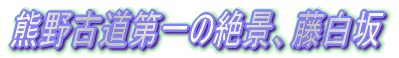
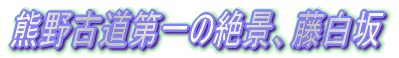
2007.3.31
午後から天気がくだりざかと報じられているが、近畿の南部は少し良さそうなので、あと2回分残っている青春18切符で熊野古道歩きに出かることにする。手元にあった関西「里山・低山歩き」というハイキングガイド本に藤白坂(熊野古道)が紹介されていた。ちょっと出かけるのが遅いが往復3時間とあるのでなんとかなりそうだ。 大阪環状線の天王寺から11時44分の和歌山行きの快速に乗る。和歌山まで1時間、御坊行きの普通列車で13分。12時過ぎにスタート地点の海南駅に着きました。駅構内で藤白神社の案内チラシ(裏面に御所の芝・塔下王子跡を往復するコースがある)をもらって出発する。 |
|
 海南駅西口を出て・・・南へ進む |
 山田川に架かる蓬莱橋を渡って、古い家並みの残る道を行く |
| スケッチしたいような家並みだが時間がないので先に進む。このコース往復するから帰り道にゆっくり描くことにしよう・・・ 町角には熊野古道の道標があるので安心して進める。 |
|
 今回歩いたコース |
|
 家並からJR紀勢線のガードをくぐってすぐに右折する分岐がある。左へ行くと汐見峠からの熊野古道になります。 |
 分岐を右へ、藤白神社へ向かう。 ところどころに熊野古道の提灯がぶら下がっている。 |
|
|
|
 |
 |
鈴木屋敷 藤白神社の手前に鈴木屋敷がありました。 ここは鈴木姓の元祖とされる藤白の鈴木氏が住んでいた所。平安末期ごろ、上皇や法皇の熊野参詣がさかんとなり、熊野の鈴木氏がこの地に移り住んで、熊野三山への案内役をつとめたり、この地を拠点として熊野信仰の普及につとめた。なかでも鈴木三郎重家や亀井六郎重清は有名で、源義経の家来として衣川館で戦死を遂げたと伝えられている。 また、重家・重清らだ幼少のころ、牛若丸が熊野往還には必ずこの屋敷に滞在し、山野に遊んだとも伝えられています。(案内板より) |
|
 藤白神社に着く。 |
 石碑と千年楠 |
藤白神社 万葉の故地「藤白のみ坂」の入り口に位置する。斉明天皇が牟婁の湯に行幸のおり神祠を創建されたとつたわる。 |
|
 |
 |
藤白神社のスケッチはここをクリックしてください。 このページに戻るにはブラウザーの「戻る」を押してください。 |
|
 わりと急な登り道となる。 |
 振り返ると海南市が・・・ だいぶ高度があがってきました。 |
 丁石地蔵が現れる |
 4丁石地蔵 |
 4丁石を過ぎたらちょっとした峠 |
 あれっ! だんだん下っていくぞ〜 |
 段々畑果樹園 |
 黒いミカンにびっくり、聞いてみると虫や鳥よけだとか、みかん作りも手間がかかるなあ・・ |
でも道は続いているので道なりに歩いて行くと展望の良い場所に出ました。 休憩&おにぎりの昼食をとりながら、スケッチをする。  海南の海が見えてくる。 ここからのスケッチはここをクリックしてください。 このページに戻るにはブラウザーの「戻る」を押してください。 丁石が見当たらないので不安になる。方向は間違っていないはずだ。通りかかった作業小屋でおばさんが仕事をしていたので道を聞く。「ここは農道で行きどまりですよ。熊野古道はこの琵琶畑の上だよ」との返事・・・ 段々畑は登りずらいので、作業用のリフトレールに沿って上がっていけばよいと教えてくれる。 登っていくと8丁石の所にとびだした。一汗かいてしまいました。やれやれ・・・ |
|
 |
 |
あとは丁石地蔵に導かられて熊野古道を進む。 |
|
 筆捨松 |
 硯石 |
| 筆捨松、その横に硯石。ここは14丁石だ。 |
|
筆捨松・硯石から坂道を登りきったところが峠でした。こんな高い所に民家があるのだ。ここから舗装路になり集落になる。 集落入口に石造宝篋印塔があり、その先の突き当りに地蔵峰寺・塔下王子がありました。 |
 石造宝篋印塔 |
 |
 |
地蔵峰寺左へいく道 熊野古道はこの舗装路を下っていく。車で地蔵峰寺と御所の芝訪れていた人にも会いました。 |
地蔵峰寺 右端のトイレと寺の間の細い道を行くと「御所の芝」に出ます。その横にJR冷水浦駅(そみずうら)への下山道があります。 |
| 熊野古道を下っていくと、前々回歩いた加茂郷からの道へ合流します。行きたいが加茂郷駅へはここから2時間とある。今日は出発するのが遅かったので加茂郷はあきらめ、冷水浦へ下山することにする。 |
|
 |
 |
御所の芝 熊野古道随一の絶景と言われている場所です。 |
|
 御所の芝からの絶景 海南市の向こうに和歌山市が展望できます。和歌の浦と弓なりの片男波(かたおなみ)もはっきり見えました。 片男波の名前の由来が万葉集の「潟を無み」からとか・・・ 「若の浦に 潮満ち来れば 潟を無み 葦辺をさして 鶴鳴き渡る」(山部赤人) |
|
 蓮如上人が休憩をとられた場所。 展望が良いと伝わっているが、いまは雑木が茂ってあまり見通しが良くない。 |
 この下山道は急な道を一気に下る。 ミカン畑から振り返って御所の芝を見る。 |
 御所の芝横から30分強で冷水浦に着く。 |
 冷水浦駅 桜が満開でした。 |