
2006・2・10

2006・2・10
 |
前回の「山背古道南部」に引き続き「山背古道北部」、JR城陽駅(城陽市)から玉水駅(井手町)まで歩いてきました。 |
| 今回はちょっと余裕を持って9時53分発の新快速に乗る。京都からおなじみの「やまとじ快速」でスムーズに城陽駅に到着しました。 JR城陽駅には山背古道の資料があると思ったのに・・・ないので、しかたなく駅前の案内地図をデジカメに納める。 9:50 出発。最初のポイントは駅から市街地歩きで十数分のところにある水度神社です。 |
 JR城陽駅、駅舎方面はなにもないが、こちら側(後方)は賑わいのある町並みです。 |
 水度神社 |
 水度神社の本殿 |
| 水度神社 鴻の巣山のふもとにある水度神社は、旧寺田村の産土神で、祭神は天照皇大御神・・・です。 「山城国風土記」の逸文に「久世の郡水渡の社祗社(くにつやしろ)」とあることから、風土記が偏された奈良時代には存在したと考えられている。 |
|
 水度神社の境内から鴻の巣山までは気持ちのいい散策路が整備されていました。参拝者や散策する人がけっこうおられました。 |
 城陽駅前の山背古道案内板より |
 鴻の巣山山頂展望台より城陽市外を望む。 |
|
 鷹の巣山頂より数分で再び展望の利く高台に出る。ここが鷹の巣展望台です。  鷹の巣展望台を振り返る 城陽市の人たちの散歩道&いこいの広場になっている。静かで良い場所でした。 山背古道はここを後にして上の案内図にある青少年野外活動総合センター(友愛の丘)に向かう。友愛の丘という看板があり。仮道のような細い道ですぐに着く。 道案内に従いここを通過して森山遺跡へ・・・ |
|
 JR長池駅近くの高台の住宅街に囲まれた中にある森山遺跡。広場に案内板があるのみ |
 長池駅方面から来たやまとじ快速 森山遺跡の高台から長池を通って市辺天満宮へと向かう。 |
 石灯篭と昔の石の道標 信号のない交通量の多い道路を横断して細い道に張ったところに分岐があり、山背路古道は右へ行く。ここで出会った京都ウオーキング協会の人に山背古道の道案内(道路上の印)のことを教えてもらいました。 |
 山背古道の目印 道標が少ないと思っていた山背古道ですが、この印が分岐にあることを知って納得しました。 その後はこの目印を頼りに歩きましたが、確認ミスして所々でコースから外れたりしました(^_^;)。 |
 梅の名所の青谷付近を歩く 前方の集落に・・・ |
 ・・・この中天満神社がありました。お参りして、コースは右へ。 |
 スケッチしたいような集落の風景。 |
 集落を外れた田園の中にまたまた天満神社がある。ここも天満神社(市辺天満神社)でした。 |
|
・・・また集落がある。この集落の道は複雑だ、何度も曲がらないと進めないが古道の目印が方向を示してくれるのでありがたい。住宅街を出ると国道307号線にでる。この道は滋賀から奈良に行くときよく通っているので見慣れた光景である。ここで右折して青谷橋まで国道歩きするが、横断しないと歩道がない。交通量が多い狭い道なので横断には十分な注意は必要です!!。 青谷橋を渡り府道を多賀駅方面に進む。ここも狭い道で車に注意していたら、左折する印を見逃してそのまま直進してしまう(^_^;)。 でも結果オーライ! しばらく行くと府道の交差点に道標があり、無事谷川ホタル公園にある高神社に着きました(午後1時)。ここで昼食にしようと思いましたが谷川沿いに広場になっていて風当たりが強くて寒い。道標にあった万灯呂山展望台(大峰 307m)までのオプションコースを歩いて展望の良いところでお昼にしようともう一頑張りすることにする。 |
|
 高神社参道入り口。 お参りはパスして万灯呂山展望台(大峰)へいそぐ。やはり低山があればついつい脱線して登ってしまう癖は直らない(^_^;)。 |
 今回歩いた万灯呂山コースです。 緑の線が本来の山背古道です。 途中に近道があるのに事前チェックしていなかったため後の祭り、大回りして時間と体力の浪費でした。 |
 山吹ハイキングコースとなっている林道を登っていく。20分ほどで分岐点がある。右:展望台まで2,300m。左:龍王瀧(350m)、遊歩道登山口(550m)。左道を選択して山吹ハイキングコースを進みました。 |
 龍王の滝分岐 滝へはこの道標の左横から谷へ下っていく。 |
 この谷川の先に龍王の滝が・・・小さな滝だが岩に隠れてうまく写せない。おまけにピンボケで写真掲載は止めました(^_^;) |
 滝口を過ぎると右手へ取り付く登山口があり、頂上まで800mとある。 頂上万灯呂展望台は山城一帯から奈良県境の生駒山まで望めました。右手には京都の愛宕山も見えました。 |
 眼下を流れる木津川と生駒山の遠望(万灯呂山展望台から) 頂上からは林道を下り元の分岐まで戻り一周したことになりました。麓まで戻ったところに「自然休養村管理センター」への分岐を見つける。谷川に沿って行く本来の山背古道をやめてこちらの道を行くことにしました。またまた脱線コースを選択・・・・ |
|
 回り道の舗装した林道の遼横には竹やぶが広がる竹の子農園になっているようだ。 山道を抜けると自然休養村管理センターと勤労者福祉会館があり、ここで山背古道に合流しました。 |
 もうすぐ前回歩いた井出町浄水場の分岐になる。ゴールが近づいてきました。 後は井堤寺跡を経由して前回行けなかった橘諸兄ゆかりの六角井戸へ立ち寄ってゴールの玉水駅を目指す。 |
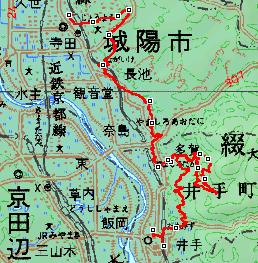 今回もハンディGPSを携帯しました。 いつも帰宅してからGPSのデータをカシミール地図ソフトにダウンロードして軌跡をたどりコースを二度楽しんでいます。失敗も脱線コースも楽しい思い出になります。 |
 井堤寺跡 井堤寺跡(いででら)は円提寺(井出寺)とも称され、天平時代の左大臣・橘諸兄(たちばなもろえ)公が、母三千代の一周忌にちなみ創建した氏寺と伝えられています。奈良時代の井堤寺は七堂伽藍の壮大な威容を誇っていたと考えられています。 出土した蓮華文の丸瓦と唐草文の平瓦復元し、この四阿(あずまや)の軒瓦として用いられていること後から知りました。なんでもデジカメメモでその場で読んでいない弊害が(^_^;)・・・ |
 六角井戸 六角井戸 天平時代の左大臣・橘諸兄(たちばなのもろえ)公は、”井出左大臣”とも呼ばれたように、ここ井出町に別荘を構え住まわれていました。 この六角形に組まれた珍しい井戸は、諸兄公の館−玉井頓宮(たまいとんぐう)のなごりとして今に伝わるもので、”公の井戸”として語り継がれている。 玉井頓宮には、聖武天皇が平城京から恭仁京(くにきょう)へ遷都される旅の終わりに、仮の宮として訪ねられたほか(天平12年(740年))、数度にわたって行幸されたと伝えられている。(案内板より転載) |
 玉川の堤防沿いを歩いてJR玉水駅へ・・・ この玉川は聖武天皇の行幸を仰いで盛大な宴遊を催したといわれる井出町の中央を東西に流れている。天平の昔に水際にくまなく山吹が植えられたといわれ、永年その美を誇った。日本六玉川の一つで古来和歌などによく詠まれています。  JR玉水駅に無事到着 GPSデータを見たら・・・ 移動距離 22km 移動時間 約5時間 休憩や立ち寄った時間を含めると6時間30分の行程でした。 |