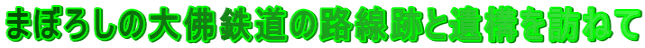
(1)
2010・2・12
| およそ100年前、わずか9年間で廃止になった関西(かんせい)鉄道・大仏線(通称大佛鉄道(奈良−加茂))の路線跡を歩いて遺構めぐりをしてきました。 |
・・・ 大仏鉄道について ・・・
関西鉄道は明治二十八年に草津・名古屋間を全通した。それから柘植から大阪方面への進出を計り、二年後の三十年十一月に加茂まで開通しまた。ここから梅谷を経て黒髪山トンネルを下り、明治三十一年四月、奈良市法蓮の大仏駅を設置した。この鉄道は、市民・観光客にも親しまれ、大仏詣での人達もこの駅で下車し一条通りを通って東大寺に参拝していた。奈良駅へはその年の十二月に到達したが、乗り入れが実現したのは翌三十二年五月であった。その後、路線が木津経由に変更となり、明治四十年八月までの約九年間で廃止された。・・・・大仏鉄道記念公園の説明板より抜粋
|
|

ランプ小屋
1897年(明治30年)10月に完成した加茂駅開業当時の建物。オランダ造り。機関車の前照灯や客車内の照明灯、列車の尾灯等の石油類を保管していました。 |
|

加茂駅
駅を出てすぐにランプ小屋(左の写真)を過ぎて、JRの踏切から写す。 |
|
|
|

大佛鉄道遺構めぐりコース入り口
踏み切りを過ぎるとすぐにこの案内板がある。
加茂小学校と線路の間を行くとSLも展示してある。
|
今日歩いた加茂駅から奈良の大佛駅跡へのルート
|

| しばらく行くと遺構めぐりの案内板のある分岐になる。直進は高田寺経由、私は右折して踏切を渡る地蔵堂経由のコースをとる。 |
|

| 踏み切を渡って、すぐ赤田川が、その橋を渡って泉川中学校の横を西へ。前方に観音寺の集落が見えてくる。集落の手前に石田部川が、この橋を渡って左折川に沿った道を進む(南へ)。田園風景が広がる。 |
|

| 左の写真に見えている白い橋のところで右折して観音寺の集落へ。集落の中の道を左折して再び南へ向かう。地蔵堂は探さず、集落を過ぎて道なりにどんどん歩く。ちょっと高台になっている道から加茂駅方面を振り返る。のどかな田園風景だ。出発地の加茂駅は写真中央の高いビルのところだ。 |
|
| この道は美加ノ原へ通じていると案内がでていたので、調子に乗ってどんどん進むとJR鹿背山(かせやま)トンネルについてしまった。観音寺橋台はこのトンネルのだいぶ手前になる。せっかっくここまで来たが、どうしても現在の大和路線と大佛鉄道が平行して走っていたという観音寺橋台を見たくて先ほど歩いた石田部川沿いの道まで戻る。川に沿って南へ進むと電車の音が、この道で間違いない・・・・道間違いで20分ほどロスする(^_^;)。 |
|
 |
 |
観音寺橋台
後方が私鉄関西(かんせい)鉄道大佛線の橋台、手前がJR大和路線です。どちらも同時期に敷いた路線らしい。 |
|
| 通り過ぎてから振り返って橋台を写す。大佛鉄道の橋台の方が背が高い。ちょうど電車が通り過ぎてしまいチャンスを逃がしてしまいました。 |
|

遺構めぐりの道と少しの間へ並走するJR大和路線
|

鹿背山トンネル
先ほど引き返した所はこのトンネルの上でした。
|

案内板に従って歩いていくと、だんだん雑木林の中へ。
|

渡るのが気味が悪いコンクリートの古い橋。
|

藪道から舗装道路へ飛び出した正面は
美加ノ原ゴルフ場のフェアウエイが見える所でした。
|

傍に石積みのしっかりした鹿背山橋台が・・・
|

| 美加ノ原ゴルフ場の正面過ぎたところに、梶ヶ谷トンネルの案内板がある。直進は大佛線の築堤、いまは市道(下梅谷〜観音寺線)として利用されています。遺構めぐりコースは左の土手下へ、すぐ右手に梶ヶ谷トンネルがあります。 |
|

梶ヶ谷トンネルをくぐる。
大佛線の築堤を造る際、農道と水路確保のために造ったトンネル。アーチはイギリス積みレンガ、側壁は御影石と贅沢な造りになっている。(案内板から) |
|

梶ヶ谷トンネル(写真の左端)をくぐってUターンして
赤橋へ向かう。
|

下梅谷の市道にある大佛線の築堤と赤橋。
ここをくぐって右へ。再び市道に戻る。
|
ちょっと長くなったのでこの続きは次のページへ
休憩です(^_^;) つづきは下記をクリックしてください。
・まぼろしの大仏鉄道遺構めぐり(2)
|
|



















